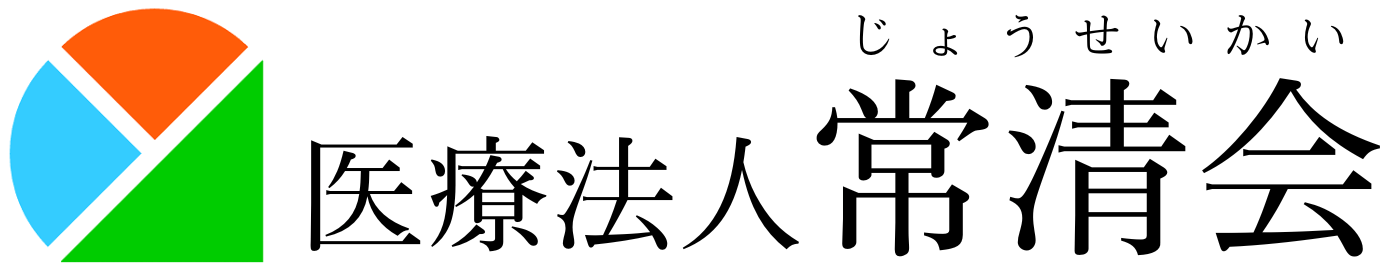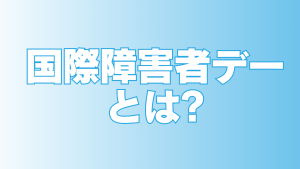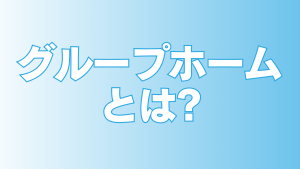精神科における作業療法は、患者が精神的な回復を目指し、日常生活の活動を通じて自己表現や社会的な役割を再構築するための支援を行う治療法です。
日本では東京都立松沢病院が初めて作業療法を導入し、現在では多くの病院や作業療法士によって実施されています。
本記事ではそんな作業療法の実践事例や日本での起源について詳しく解説します。
作業療法とは?
作業療法とは、日常生活で必要な動作や活動を通じて、身体的・精神的な機能を回復・改善する支援を行う治療法です。ここで言う「作業」とは、患者の精神的、社会的な回復を促進するための重要な手段となっています。
作業療法では以下のような活動をしています。
- 日常生活動作(ADL:Activities of Daily Living)の訓練
- 認知機能の向上を目指した活動
- 情緒の安定やストレスマネジメントに繋がる活動
- 創造的な活動や趣味活動
これらの活動を通じて患者は自分自身の価値や社会での役割を再認識し、回復への道を歩むことができます。
作業療法の目的
作業療法の主な目的は、患者が自立した生活のために必要な能力を回復させることです。 特に精神科の患者においては、社会生活の中での機能回復が中心となります。目的としては以下のようなものが挙げられます。
- 社会参加の促進:患者が社会の一員として自立し、活動するための支援をします。
- 情緒や精神の安定性:疾患による不安や抑うつを減らすために、リラクゼーション技法やストレス管理の手法を取り入れます。
- 認知機能の改善:作業療法による訓練を行い、患者の認知力や判断力を高めます。
- 社会的スキルの向上:他者とのコミュニケーションスキルや協調性を学び、社会的に適応できる能力を高めます。
日本における精神科の作業療法の起源と歴史
東京都立松沢病院が日本で初めて作業療法を導入した精神科病院として知られています。
導入された年は1925年(大正14年)でした。
当時の精神科医療における治療法は薬物療法が中心で、患者は一時的に病院に収容されることが一般的でした。
しかし松沢病院が作業療法を導入したことで日本の精神科医療は大きく変わっていきます。
1950年代に入って本格的に作業療法が導入され、1954年には日本作業療法士協会が設立。
作業療法士の資格が生まれ、作業療法士の教育や研修も本格的に始まりました。
その後多くの精神科病院やリハビリテーション施設でも作業療法が取り入れられ、現代では精神疾患の一般的な治療方法となりました。
精神科における作業療法の実践例
手工芸やクラフト作業
手工芸やクラフト作業は、患者の集中力や手先の器用さを養うために行われる一般的なリハビリです。
精神疾患によって損なわれた集中力や自尊心の回復のために、以下のような活動が行われます。
- 編み物や刺繍:手を動かすことでリラックス効果があり、完成した作品が自己肯定感を高めるのに役立ちます。
- 絵画や陶芸:創造的な活動を通じて患者の感情を表現したり、リラックス効果を得ることができます。
- 木工や模型作り:物理的な作業に取り組むことで、注意力を鍛え達成感を感じることができます。
日常生活動作訓練(ADL訓練)
精神科患者の中には、日常生活に必要なスキル(ADL:Activities of Daily Living)の習得が難しい場合もあります。
患者が自立して生活できるようにサポートするために、以下の訓練を行うこともあります。
- 料理:簡単な料理をすることで、食事の準備スキルを向上させながら、自己管理能力を高めることを目指します。
- 掃除や洗濯:家庭で必要となる掃除や洗濯の手順を学び、実践的な生活スキルを身につけます。
- 金銭管理:お金の使い方や買い物の練習を通じて、経済的な自立を目指します。
グループ活動・共同作業
社会的な孤独感を解消し、他者との交流を深めることは精神疾患の治療では重要です。
- 料理や食事作り:グループで食事を作ることで、協力し合う能力を育むだけでなく、日常生活に必要なスキルを養うことにもつながります。
- 掃除や整理整頓:共通の目的に向かって作業を行うことで患者間での協力関係を強化し、日常生活における役割を再確認することができます。
- 演劇や音楽活動:演技や音楽の活動を通じて表現力やチームワークを学び、患者同士の幅広い関係を築くことができます。
リラクゼーション法やストレス管理
精神疾患の患者にはストレスや不安を抱える人が多いため、作業療法ではリラクゼーション法を取り入れています。
- 深呼吸や瞑想:呼吸法や瞑想を学ぶことで、リラックス効果が期待されます。
- ヨガや軽い体操:身体を動かすリラクゼーション法で、心身の緊張をほぐせます。
- 音楽療法:リズムやメロディを使って感情の安定を図り、精神的にリラックスできます。
自立支援プログラム
精神科における作業療法は、患者の社会復帰を目指す支援にも焦点を当てています。
患者が社会に適応するためのスキルを向上させるために、作業療法士が職業訓練や就労支援プログラムを実施します。
- 職業訓練や就労支援:患者の職場での適応力を高めるために、職場を想定した仕事や就職活動の支援を行います。
例えば、パソコンを使った事務作業や接客業のシミュレーションなど。 - 社会的スキルの訓練:面接の練習、電話対応、対人スキルの向上を図るための訓練が行われます。
感情表現のサポート
患者の中には自分の感情をうまく表現できない方もいます。
作業療法では感情を表現しやすいように話す以外にもサポートを行います。
- アートセラピー:絵や彫刻などを通じて感情を表現しやすくし、自分の気持ちを視覚的に表現します。
特に感情を言葉にすることが難しい患者にとって、アートは有効な表現手段となります。 - 書くこと:日記や詩を書くことで感情を整理し、自分の思考を明確にできます。
認知リハビリテーション
抱えている精神疾患によっては、認知機能に障害が現れることもあります。
認知リハビリテーションでは、低下した認知機能を高めるための活動が行われます。
- パズルやボードゲーム:ゲームを通じて、思考力や問題解決能力を向上させる訓練を行います。
- 記憶力のトレーニング:カードや写真を使った記憶ゲームなどを活用して、記憶力や集中力を鍛えます。
「作業療法士」の役割
作業療法を中心に患者の心身の回復を支援する作業療法士。
作業療法士として働くためには専門学校や大学で作業療法を学び、国家試験「作業療法士」に合格する必要があります。
そんな作業療法士は主に以下のことを行います。
- 患者の状態の評価:患者の身体的・精神的な状態を捉え、作業療法が有効な支援となるよう個別の治療計画を作成します。
- 治療計画の実施:個別の治療計画に基づいて、日常生活動作の訓練やリハビリテーションを行い、患者が社会で自立できるように支援します。
- 家族や介護者サポート:患者の家族や介護者に対して、生活支援の方法を指導し、地域社会での自立をサポートします。
作業療法士は、患者と並走しながら社会復帰に向け具体的な支援を行う重要な存在です。
作業療法は患者の回復と社会復帰を支える重要な治療法
精神科の作業療法はますます重要になってきており、社会復帰支援や患者のQOL向上のために支援方法も多様化しています。病院によってリハビリのプログラム内容も異なり、中にはデジタル技術の進化により遠隔での作業療法やVR(仮想現実)を活用している場所もあります。
医療法人常清会は患者様に寄り添った医療を提供できるようにこれからも努めていきます。
お困りの方がいましたら気軽にお問い合わせください。